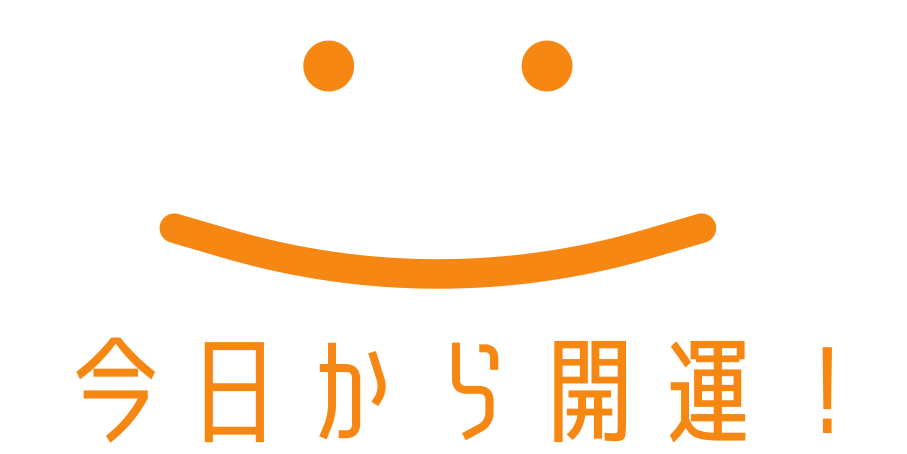亥の子餅と十日夜で開運!
亥の子餅とは
亥の子餅(いのこもち)は、旧暦10月(亥の月)の最初の亥の日に、家々で無病息災と子孫繁栄を祈って食べられてきた、日本の古い年中行事です。とくに西日本(山陰・山陽・四国・九州)で古くから親しまれてきました。
由来は平安時代。宮中で行われていた「御亥猪(おげんちょ)」という行事が元とされます。十二支の「亥」は万病を退ける力の象徴とされ、亥の月・亥の日・亥の刻が揃う「三りゅう=最強の厄除け日」に、餅を食べて邪気払いをしたのです。
亥の子餅は、その年に収穫した、米・大豆・小豆・笹下・胡麻・栗・糖の、7つの粉を混ぜてついた餅のこと。現在では、特に決まった形はなく、さまざまな亥の子餅が売られています。
現在では11月の最初の亥の日に行う地域が多く、家族円満・健康長寿・厄除けの開運日として再び注目されています。
亥の子餅の日にすると良いこと2つ
家の四隅を軽く突いて、地の気を整える
古くは子どもたちが、亥の子石と呼ばれる丸い石に縄を付け、石を上下に動かして地面を突く風習がありました。
それにあやかり、家の四隅を軽くトントンと突いてみましょう。地の気が整い、家庭運が安定します。
炬燵を出すなら、亥の子餅の日に
「亥」は水の気で、火除けのパワーがあります。江戸時代、最初に炬燵に火を入れる日は、この日がよいと信じられていました。
同じく火鉢を使う茶の湯でも、この日が炉開きの日。開炉の茶事では、亥の子餅がお茶菓子として出されます。
というわけで、炬燵(に限らず暖房)を出すなら、亥の子餅の日に。できれば、亥の月・亥の日・亥の刻に。
十日夜とは
十日夜(とうかんや/とおかんや)とは、旧暦10月10日に行われる「収穫を終えた田の神をお送りする行事=収穫祭」です。
主に東日本(関東~甲信越~東北)が中心で、西日本の亥の子行事と対になる年中行事です。
旧暦10月10日は、新暦だと11月中のどこかになることが多く、2025年は11月29日となります。
春、山から降りて田んぼに「田の神さま」が降り、秋の収穫を終えると再び山へ戻ると考えられていました。十日夜は、田の神さまをお見送りする日。お餅やぼた餅を供えて見送ります。
地域によっては「藁(わら)鉄砲」を打ち合い、悪霊を祓い清めたり、豊作を祝ったりも。来年の豊作と家内安全を祈り、1年の実りを振り返ります。
そして年越しの準備…師走・12月を前にした、秋と冬の節目となるのです。
十日夜の日にすると良いこと2つ
お月見~月に願いを
十日夜は、新月ら10日目の月のことで、上弦の月(🌓)よりもやや膨らんだ形です。
10月まで、十三夜、十五夜、十六夜、と、縁起の良いお月見の日がありました。十日夜は、月に願いを告げる、年内最後の日なのです。
藁や紙で作った「簡易藁鉄砲」で邪気払い
かつて十日夜の夕方~夜にかけては、藁を固く巻いて棒にした「藁鉄砲」で地面をたたき、害獣を駆除し、豊穣を祈ったといいます。
それにあやかって、藁鉄砲で厄払いをしましょう。藁が手に入らないのなら、紙を丸めたものでで軽く床をトントンと叩くだけでもOK。空間の厄が抜け、家の運気が上がります。
亥の子餅と十日夜
西日本で行われる「亥の子餅」、東日本で行われる「十日夜」。
「実りに感謝し、邪気を祓い、冬への準備を整える」日本ならではの開運行事。餅をいただき、家を整え、神さまに感謝するだけで、11月の運気は安定し底上げされます。
自分の住む地域に合わせ、ぜひ開運アクションを実践してみてください。