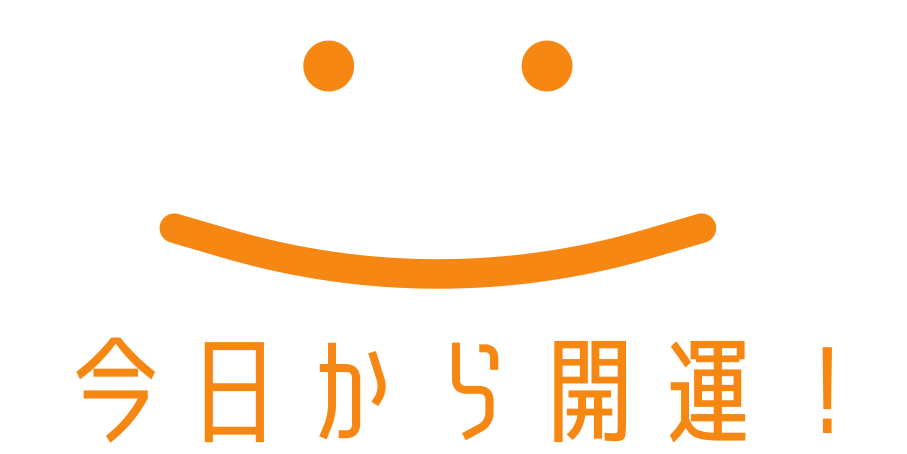9月9日の「重陽の節句」は、五節句のひとつで長寿や繁栄を祈る日。由来や歴史を学び、菊や食の習わしを取り入れて、日常で実践できる開運法を紹介します。
重陽の節句とは
重陽の節句(ちょうようのせっく)は、毎年9月9日に行われる五節句のひとつです。奇数は陽数とされ、なかでも最大の「9」が重なるこの日は「陽が重なる」として尊ばれました。中国では古くから厄を祓い長寿を願う日とされ、菊の花や菊酒を用いて不老長寿を祈る習慣がありました。日本には奈良時代に伝わり、平安貴族の間では菊の花を愛で、和歌や宴を楽しむ行事として発展しました。
「菊の節句」とも呼ばれるのは、この日が菊の見頃と重なったためです。菊は邪気を払う花とされ、菊を浸した酒や、菊の花びらを浮かべた水をいただくことで、心身を清めると信じられてきました。
また9月9日は、中国では登高と呼ばれ、山へ登って災厄を避ける風習があります。現代の日本ではあまり大々的に祝われませんが、行事食として栗ごはんや秋の味覚を楽しみ、長寿や健康を願う日として再び注目されています。
重陽の節句の前後にするといい開運法 3つ
重陽の節句で開運 その1. 菊風呂で邪気を祓う
重陽の日には、菊の花を浮かべた「菊湯」に入るとよいとされます。菊には浄化作用があると信じられ、花の香りや気を浴びることで心身を清め、邪気を払いのける効果が期待できます。実際に入浴剤やハーブ代用でも構いません。浴槽に花を浮かべる習慣は見た目も華やかでリラックス効果が高く、重陽の夜にぴったりです。風水的にも「水」は運を流す力があるため、菊風呂は開運力を高める実践的な方法となります。
重陽の節句で開運 その2. 栗ごはん
重陽の節句には「栗の節句」とも呼ばれるほど、栗を食べる習慣がありました。秋の実りを象徴する栗は、豊かさと繁栄の象徴です。とくに「栗ごはん」をいただくことは、金運・食運を呼び込む開運食とされます。ご飯に甘栗や塩ゆで栗を加えるだけでも実践可能。風水では「丸い食材」は円満を表すため、家庭の和合にもつながります。家族そろって栗ごはんをいただくことで、秋の恵みを感謝と共に味わい、運気の底上げを図ることができます。
重陽の節句で開運 その3. 菊を飾り長寿と良縁を招く
菊は「延命長寿」の花として尊ばれ、邪気を遠ざける力があるとされます。玄関やリビングに菊の花を飾ることで、家の中に清らかな気が流れ込み、空間が明るく整います。黄色の菊は金運を、白い菊は浄化を、赤い菊は愛情を象徴するとされるため、願いに合わせて選ぶのもおすすめです。フラワーアレンジや一輪挿しでも十分効果的。飾った花に日々感謝を伝えることで、良縁を呼び込み、心身ともに健やかな運気を整えることができます。