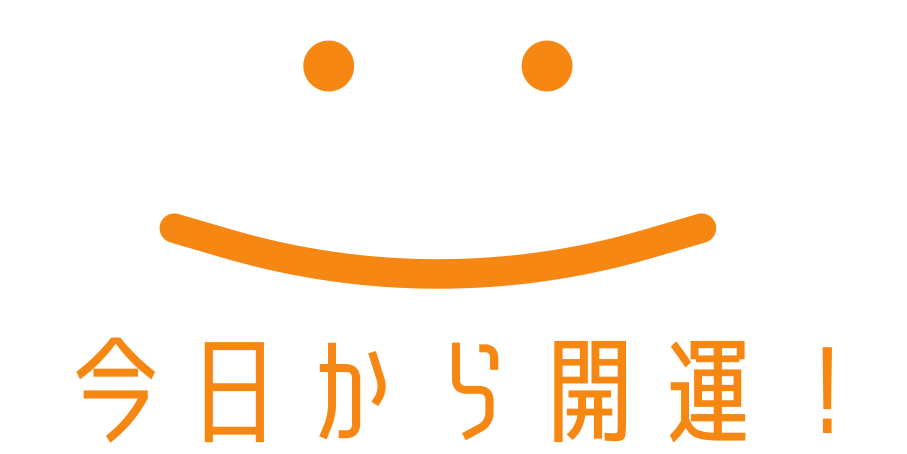日本人の心の花「桜」。桜の化身である神様・木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)は、女性の味方の神様です。桜パワーは女性の魅力をアップ! お花見に桜餅、桜茶など、桜パワーを取り入れる方法をお伝えします。
日本列島お花見事情
3月も半ばになれば、日本各所で桜便りが聞かれるとともに「お花見」シーズンに突入します。
日本は南北に長いので、実は1月上旬の沖縄から7月の北海道や北アルプスまで、桜前線が続くのです。
1月に開花を迎える沖縄では、本島北部の八重岳・名護城・今帰仁などが桜の名所として知られます。そこから順次東進し、東端の北海道・根室では5月中~下旬に国後島から移植された「千島桜」が開花を迎えます。
5月~7月にかけて、南北アルプス、八ヶ岳連峰、東北地方の高地と開花していきます。桜を追っていけば、日本縦断ができてしまうのです。
桜のお花見をしているのは世界的には日本だけで、桜の自生が日本より古いインドや中国でも、桜宴は行われませんでした。
また、ニュースなどで、ワシントンのポトマック河畔でアメリカ人がお花見をしているのを観ることがありますが、これは逆輸入のお花見で、桜を特別視していたのはどうやら日本だけのようです。
かつて、お花見は農業行事のひとつでした。
平安期に入り、貴族や殿上人が桜の下で歌会や舞いの宴を催すようになりました。現在のお花見スタイルは、江戸時代に始まりました。
桜の時期、桜パワーを取り入れよう
桜の花で開運 1.桜茶・桜餅を食べる
古来より、桜は豊かな実りと幸せを運ぶものとされています。
「桜茶」はおめでたい席、特に結納の席には欠かせません。「花開く」という意味を持って出されます。塩漬けした桜の花びらに、お湯を注いだお茶です。別名は「桜湯」。
また「桜餅」は、ひな壇の前に供えて女の子の健やかな成長を願うものですが、葉っぱごと食べることによって、桜の持つ強力な開運エネルギーを取り込めます。
長命寺 vs 道明寺
桜餅は、こし餡を桃色に着色した生地で包み、塩漬けした桜の葉を巻いた餅のお菓子。しかし、この桜餅は「関東では長命寺」「関西では道明寺」と呼ばれ、名前も作り方も微妙に違います。
関東では小麦粉の焼皮をクレープ状に巻きます。
関西では、糯米を蒸かして乾燥させ、粗く砕いた粒(つぶ)のある道明寺粉の皮で、饅頭のように小豆餡を包んだ物です。
関東地方では関西風の桜餅を道明寺と呼びますが、この呼び方は関西では一般的ではありません。
桜の葉の独特の香りは、塩蔵するときに分解して生成したクマリンという物質に由来します。このクマリンには肝毒性があるので、おいしいからといって、食べすぎには注意です。桜の葉を取って食べるのか、取らずに一緒に食べるのかについて議論がありますが、葉は本来取って食べていたもののようです。
桜の花で開運 2.木花咲耶姫に感謝を捧げる
桜の木に縁の深い神様といえば、「木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)」。木花咲耶姫は、全女性の守り神。「木花」とは、桜の花のことです。
桜の花には、幸運の気が満ちています。木花咲耶姫に日々感謝すれば、女性としての魅力がアップ! 恋愛運・結婚運・家庭運に恵まれるでしょう。
木花咲耶姫をご祭神とするのは浅間神社です。全国に約1300社ありますので、ぜひ参拝して魅力運をアップさせましょう。
ところで、「桜」の旧字体「櫻」の「嬰」の字は、二つの「貝」と「女」から成り立っています。「貝」はかつて装飾品でした。ふたつ並んだ「貝」は首飾りのこと。「嬰」は首飾りをつけた女性の意味です。桜の木は、女性そのものなのです。
桜の花で開運 3.お花見に出かける
桜の花には、ポジティブになれる力が宿っています。その力がフルパワーとなるのは、やはり満開のタイミング。満開の地を探して、お花見に出かけてください。
お花見には「神と人が飲食をともにする」という意味があります。
見て愛でるだけでなく、「花より団子」を実践することで、神様との距離が縮まります。食べる前に、心の中でいいので、神様にお供えをするとよいでしょう。
桜パワースポット おすすめ2か所
日本中に桜の名所はありますが、桜パワースポットとして2か所をおすすめします。
吉野山の桜
奈良県の吉野山は、桜の名所として知られています。一目見れば桜が千本見えるといわれ、しかも、上千本・中千本・下千本、そして奥千本と、4つのエリアでそれぞれ千本見える豪華さです。
吉野の山では山岳信仰が盛んで、修験道の開祖である役行者(えんのぎょうじゃ)が蔵王権現を感得したとき、桜の木でその姿を刻んだといいます。以来、吉野の桜は神木になりました。
金櫻神社(かなざくらじんじゃ)
金櫻神社は、山梨・甲府の名勝、昇仙峡を登りつめた地にあります。神社名の由来ともなっているのが、ご神木の「鬱金桜」。鬱金色の花びらが特徴的で、古くから「金の生る木」と崇められています。
金櫻神社のご神体である金峰山も、修験道の霊場です。