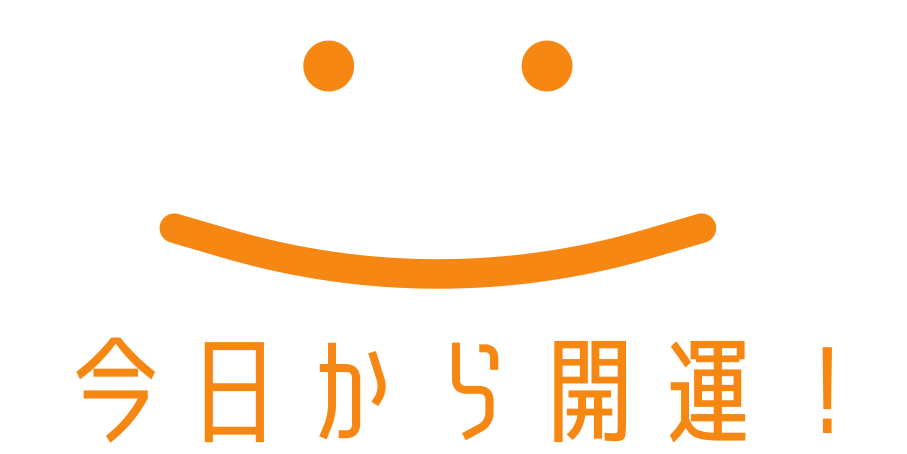節分に豆をまき、恵方巻を食べるのは、なぜなのでしょう。
2026年午年の節分は2月3日の水曜日。節分は冬と春の分かれ目のことで、旧暦では1年の終わり。次の日の2月4日は立春です。
この記事では節分の、由来と歴史、厄払い、開運の意味を説明します。
節分とは
節分はもともと「季節を分ける」という意味で、立春・立夏・立秋・立冬の前日を指すものです。
本来は四季のタイミングで年4回やってくるのですが、特に旧暦の立春は1年の始まりとされ、今の大晦日にあたるような重要な日だったため、現在では立春の前日にあたる2月3日前後を節分というようになっています。
節分の日に行う行事は、旧暦の新年とされる2月4日の立春を迎えるにあたり、1年間の厄を払い、新年の幸福と無病息災を願う儀式として人々の間に定着してきました。
近年では家の事情などで行事をしない家庭も増えたようですが、その家に合った方法でかまいませんので、きちんと行うことをオススメします。
節分に、なぜ豆をまく?
節分といえば豆まき。煎った大豆が主流ですが、片付ける手間を考えて殻付き落花生を投げることも多いようです。
しかし、そもそも、なぜ「豆」なのでしょうか?
豆で鬼(厄)を追い払う
「鬼は外、福は内」と唱えながら行う豆まきは、中国から伝わった「鬼やらい」という行事が発祥とされています。
これは大晦日に宮中で行われていた行事で、定められた者が桃と葦でできた弓矢を持ち、呪師となって無形の鬼を追い払うというもの。
それが民間も普及し、今のような形になったとのことです。
鬼を払うのに豆を投げるのは、豆は「魔滅(まめ)」という意味に通じ、魔除けの効果があること、中国の医書に「大豆は鬼毒を消して痛みを鎮める」と書かれていたこと、豆は穀物の中でも大変硬く、当たると痛いこと……などなど、多くの理由があるようです。
豆まきは、陽の気が強い午前中に行うのが吉となります。
豆を食べれば無病息災
豆まきの豆を、数え年(年齢+1)の数だけ食べると、これから1年間は健康に過ごせると言われています。
年齢よりも1つ多いのは「新年を越す」というところから。
豆は「魔眼(まめ)」に通じ、鬼そのものを表すという説もあり、豆(=鬼)を食べて撃退するという意味が込められているそう。
豆まきに使う炒った大豆は邪気が払われた「福豆」となります。食べることで無病息災を願うとともに、身体の中に福を取り込むことにもなるのです。
しかしながら、毎年きちんと食べている人は意外と少ないのではないでしょうか。
「年の数だけ食べるのは大変」という人は、適当な数の福豆を入れてお茶を注いだ「福茶」を飲むことで、豆を食べたのと同じご利益を得られます。
それでも、年の数だけ豆を食べて、雰囲気を味わいたい! という人には、ゆで豆がおすすめです。
節分に、なぜ恵方巻を食べる?
開運の方位に向かい、もぐもぐと途切れさせることなく巻き寿司を食べきる、というのが「恵方巻」の正式な作法であるとされています。
よって、最初のころは、細巻でした。しかし、だんだん具が豪華になり、絶対に口に入りきらない大きさの太巻きに変化。
もはや節分は、恵方巻という名の巻き寿司を食べる日となりましたが、「巻き寿司」にはとても縁起の良い意味があるのです。

福を巻き込む巻き寿司
恵方巻が巻き寿司なのは、「七福神になぞらえた七種類の具(福)を巻き込む」というところからきているとか。
また、一本の巻き寿司を切らずに丸ごと、できるだけかみ切らずに無言で食べる理由は「福縁が切れないように」という願いが込められているからなのです。
恵方巻=福を食べて開運。2026年(丙午年)の恵方は「南南東やや南」
「恵方」とは、年の福徳をつかさどる吉神(歳徳神)がいる方角のこと。恵方巻は、この恵方に向かって巻き寿司を食べると開運できるという風習です。
恵方巻の由来は諸説あるようですが、節分の夜、関西の花街でお新香を巻いたお寿司を食べたことが始まりとも言われています。
ここ最近、スーパーやコンビニなどが季節品として扱うようになってから一般化し、今や全国区となりつつあります。
恵方は毎年変わり、2026年(丙午年)の恵方は「南南東やや南」。
恵方へ向いて恵方巻を食べると、丙(火)の勢いを良い方向へコントロールでき、開運の流れをつかみやすくなります。
節分は、豆をまいて恵方巻を食べよう
節分は、自然と四季を大切にしてきた日本の、古くからある年中行事です。
豆をまいて去年までの厄をしっかり払い、恵方巻で福を招き入れ、新年のはじまりとなる2月4日の「立春」を迎えましょう。