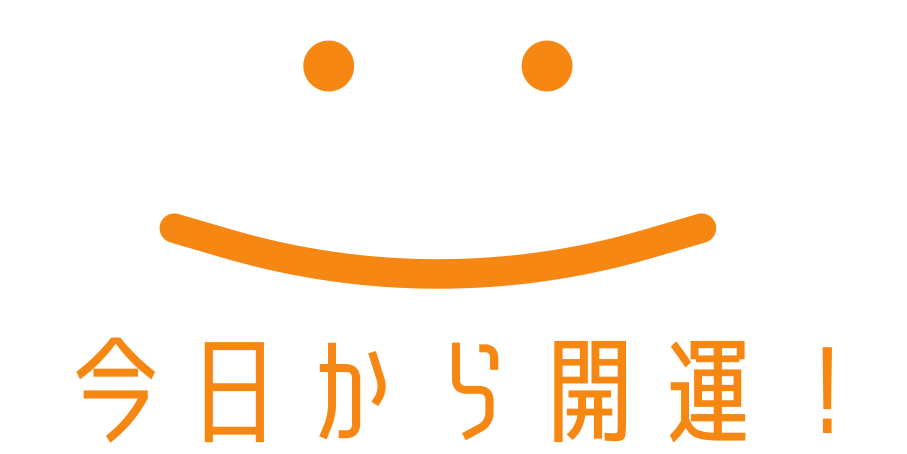お盆って、東京周辺が7月、その他地域は8月と、時期が違うんです。7月盆(新盆)、8月盆(旧盆)と呼ばれ、その理由は、改暦に伴って時期がずれたことや、農作業の都合などがあります。
7月盆(新盆)も8月盆(旧盆)も、ご先祖様の霊を迎える行事であることに変わりはありません。ご先祖様を迎えて供養することは、自身の幸せへとつながります。
今回は、8月盆に行う、盆の行事内容を紹介します。
お盆とは ~7月盆(新盆)と8月盆(旧盆)
お盆は7月盆(新盆)、8月盆(旧盆)、または旧暦7月に行われ、どの月でも13~16日がお盆のメインです。会社の夏休みなどの関係で、8月がお盆休みと呼ばれています。故人の死後、初めて迎えるお盆のことも新盆と呼びます。東京は7月盆なので、そのころから夏祭りと盆踊りが行われ始めます。
盆は、先祖や亡くなった人の霊を迎え、供養する行事です。正式には盂蘭盆会。7月盆(新盆)は、七夕の頃になったら、盆の準備を始めましょう。8月盆(旧盆)は、8月10日くらいにははじめたいですね。
お盆に道具は、時期が近づくとスーパーや花屋などで、お盆セットとして売られます。セットの内容にもよりますが、2000円~くらいでそろいます。
また、お供えとして、かごに入った野菜や果物のセットも、八百屋さんなどで見ることができます。
ご先祖様を迎え幸せを呼ぶ、お盆の行事内容
お盆で開運 1.精霊棚をしつらえる
まず、供養のための精霊棚(盆棚)を作ります。盆棚とは、亡くなった人の霊のために、特別にしつらえる棚のことです。小机を用意しましょう。
精霊棚(盆棚)に真菰(まこも)を敷き、蓮の葉に載せた盆菓子、真菰縄(まこもなわ)に旬のものを挟んで飾り、お供えの食物、牛馬、盆花を供えます。両隣に盆灯籠(盆提灯)を置きます。
お供えは、初物の農作物(きゅうり・なすなどの夏野菜や果物)、供養膳として精進料理を盛りつけます。「見て美しく」飾ってあげることを心がけると、ご先祖様も大変喜ばれるでしょう。
お盆の時期は、お墓や仏壇のお供え物と同じもの、それも肉や魚を使わない「精進料理」を食べます。「そうめん」「天ぷら」「団子」などが一般的です。私たちはご先祖様をお迎えする立場ですから、ご先祖様とは違う自分の好きなものを食べるのはマナー違反となります。
とはいえ、精進料理とは関係なく、故人の好きだったものをお供えし、食するのは、ご先祖様を偲ぶことになりますので、大丈夫です。
お盆で開運 2. 牛馬
精霊棚に供えるキュウリで作った馬には、先祖の霊が馬に乗って一刻も早く家に戻るように、ナスで作った牛には、あの世に帰るのが少しでも遅くなるように、また供物を牛の背に乗せて持ち帰ってもらおうという願いが、それぞれ込められています。
お盆で開運 3. 13日に迎え火、16日に送り火
13日の「お盆の入り」の夕方、家の門口や玄関で素焼きの焙烙(ほうろく)に、オガラと呼ばれる皮を剥いだ麻の茎を折って積み重ね、火を付けて燃やし、迎え火を焚いてご先祖様をお迎えします。
16日の「お盆の明け」には、ご先祖様に無事にお帰りいただくために、迎え火と同様の形で送り火を焚きます。
8月16日の有名な京都の大文字焼は、「五山の送り火」。お盆を締めくくる送り火なのです。